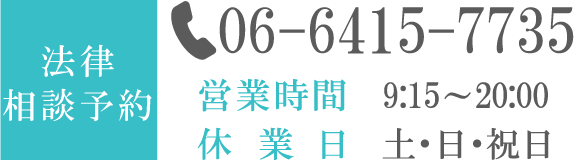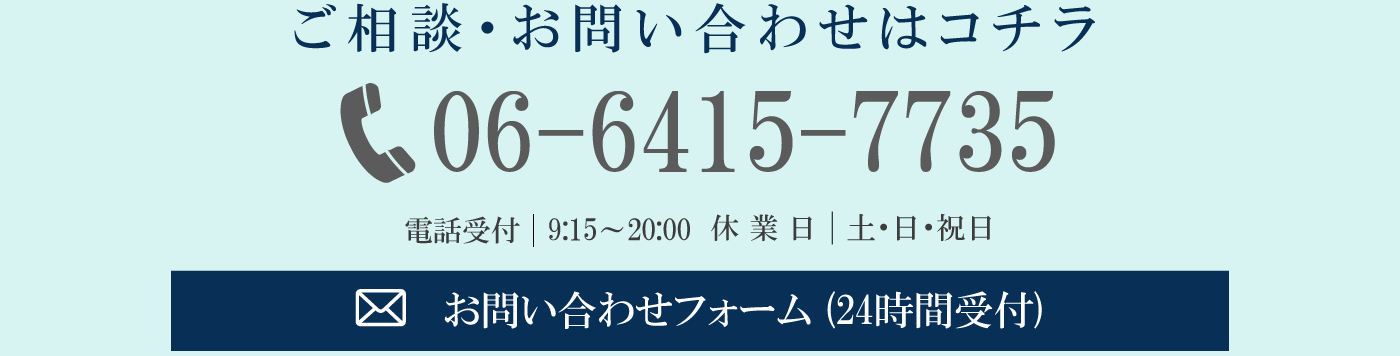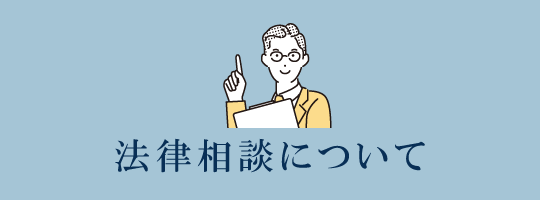このページの目次
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦及び子供が生活をするために必要な生活費のことで、具体的には、衣食住にかかる費用・医療費・交際費・子供の教育費などが該当します。
民法第760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しているため、夫婦はそれぞれの能力に応じて家庭全体の生活費(婚姻費用)を分担しなければなりません。
相手方が負担すべき婚姻費用(生活費)を支払うよう請求することを婚姻費用分担請求といいます。
婚姻費用を請求できる場合
婚姻費用は、婚姻中であれば請求できるのが原則です。婚姻費用は、別居中であっても請求できますし、自ら家を出て別居を開始した者からも請求できるのが原則です。
さらに、婚姻費用は夫婦関係が破綻した後も請求することができるのが原則ですが、不貞などの有責配偶者からの請求は認められない場合もあります。
養育費との違い
金額
妻と子供が同居しているという例で説明をしますと、婚姻費用には妻と子供の生活費が含まれていますが、養育費に含まれているのは子供の生活費だけです。従って、夫婦の収入が同じであれば、養育費よりも婚姻費用の方が高額になるのが原則です。
期間
婚姻費用について定めた民法第760条は、「夫婦は」と規定していますので、婚姻費用を請求することができるのは離婚が成立するまでです。結婚をしている間の子供の生活費は婚姻費用として支払われますので、養育費は離婚後から請求することとなります。
離婚前は婚姻費用、離婚後は養育費ということです。
婚姻費用の金額
婚姻費用の金額を簡単に調べる方法
裁判所のHPに掲載されている表(以下「算定表」といいます。)を見ることでおおよその金額を知ることができます。
算定表を使う際の初歩的な注意点
- 婚姻費用の算定表を使ってください(養育費の算定表を使わないでください)。
- 婚姻費用の算定表は10種類(表10~表19)ありますので、お子様の数と年齢にあわせて正しい表を選んでください。
- 算定表に書いている「権利者」は婚姻費用を受け取る者、「義務者」は婚姻費用を支払う者を意味しています。
- 給与所得者の収入は、源泉徴収票の「支払金額」の欄を見てください。
- 自営業者の収入は、確定申告書の「課税される所得金額」に、実際に支出されていない費用(基礎控除や配偶者控除や青色申告特別控除など)を加算して決めるのが原則です。自営業者の収入は、確定申告書の数値が信用できるのかも含めて争いになることが多いです。
- 児童手当は権利者の年収に加算しません。
婚姻費用の金額の計算式
家族構成があてはまらないなどの理由で算定表を使えない場合、裁判所は「標準算定方式」と呼ばれる計算式で婚姻費用の金額を算出するのが一般的です。標準算定方式は、給与所得者・自営業者いずれの場合にも使用されます。
標準算定方式で婚姻費用を算出する際は、以下の4ステップで計算を行います。
ステップ1
夫婦それぞれの総収入を確定する
総収入とは、文字どおり収入の総額を意味しています。
給与所得者であれば、源泉徴収票の「支払金額」や課税額証明書の「給与収入」の金額が総収入となります。総収入を計算する段階では、所得控除や社会保険料の控除はしません。
自営業者の総収入は、収入(売上)ではなく所得(売上から必要経費を引いたもの)に着目をして計算をします。具体的には、確定申告書の「課税される所得金額」に、実際に支出されていない費用(基礎控除や配偶者控除や青色申告特別控除など)を加算するという方法がよく使われています。
ステップ2
夫婦それぞれの基礎収入を算出する
基礎収入とは、総収入のうち生活費に充てられるべき金額をいいます。
ステップ1で確定した総収入の中には、税金や社会保険料などの支払にあてなければならない金額が含まれています。総収入からこれらの金額を差し引くことにより、夫婦が自由に使える金額を計算したものが基礎収入です。
基礎収入は、総収入から以下の3類型の金額を差し引いて算出します。
〈総収入から差し引く金額〉
- 公租公課 所得税、住民税、社会保険料です。
- 職業費 給与所得者として収入を得るために必要な経費です。
具体的には、被服費・交通費・通信費・書籍費・諸雑費・交際費などが該当します。 - 特別経費 従来は事例ごとに様々な支出が特別経費に該当するかが争われていましたが、現在は、住居関係費・保健医療費・保険掛金が特別経費に該当すると扱われています。
基礎収入の計算は、総収入から公租公課・職業費・特別経費の実額を差し引くのではなく、統計上の数値をもとにした一定割合を控除するという方法で行います。簡易迅速に計算を行うためです。
上記のような考え方のもと、実際には、総収入に以下の割合(基礎収入割合)を掛けることで基礎収入を算出しています。
具体例を挙げますと、例えば総収入が500万円の給与所得者の基礎収入は、500万円✕42%=210万円となります。
|
基礎収入割合 |
|||
|
給与所得者 |
自営業者 |
||
|
総収入(万円) |
割合 |
総収入(万円) |
割合 |
|
0~75 |
54% |
0~66 |
61% |
|
~100 |
50% |
~82 |
60% |
|
~125 |
46% |
~98 |
59% |
|
~175 |
44% |
~256 |
58% |
|
~275 |
43% |
~349 |
57% |
|
~525 |
42% |
~392 |
56% |
|
~725 |
41% |
~496 |
55% |
|
~1325 |
40% |
~563 |
54% |
|
~1475 |
39% |
~784 |
53% |
|
~2000 |
38% |
~942 |
52% |
|
~1046 |
51% |
||
|
~1179 |
50% |
||
|
~1482 |
49% |
||
|
~1567 |
48% |
||
※自営業者の基礎収入割合が給与所得者の基礎収入割合よりも高くなっているのは、自営業者は総収入を確定するステップ1の段階で社会保険料と職業費が既に控除されているためです。
※総収入が2000万円(自営業者は1567万円)を超える場合、対応する基礎収入割合表がありません。このような高額所得者の婚姻費用については後述します。
ステップ3
夫婦の基礎収入を合算した金額を2つの世帯に振り分ける
ステップ2で計算した(夫の基礎収入+妻の基礎収入)を、夫の世帯と妻の世帯に振り分けます。振り分けを行うにあたっては、生活費指数という以下の数値を使用します。
| 生活費指数 | |
| 夫 | 100 |
| 妻 | 100 |
| 14才以下の子 | 62 |
| 15才以上の子 | 85 |
具体例を使って説明をしますと以下のようになります。
【事例】
夫:基礎収入 392万円、一人で生活
妻:基礎収入 94万円、8歳の子、11歳の子と同居
【妻の世帯に振り分けられる基礎収入】
(392万円+94万円)✕(100+62+62)÷(100+100+62+62)=336万円
ステップ4
義務者が負担する婚姻費用の額を算出する
ステップ3の事例では、妻に振り分けられるべき基礎収入額が336万円と計算されましたが、現実には妻の基礎収入額は94万円しかありません。
そこで、夫は差額の242万円(336万円-94万円)を婚姻費用として妻に支払うべきこととなります。242万円は1年あたりの支払額ですので、夫が支払うべき1ヶ月あたりの婚姻費用は20万1666円となります。
婚姻費用を請求する手続
夫婦間の協議
婚姻費用の額は、協議ができるときは夫婦間の合意で決めます。夫婦間で合意をできるのであれば、裁判所が作成した婚姻費用算定表と異なる金額を取り決めることも可能です。
夫婦間での協議が調った後は、内容を明確にするために合意書を作ったり、支払の不履行が予測される場合などには婚姻費用分担契約公正証書を作るという対応をした方が良い場合もあります。
調停
夫婦間の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申立し、調停で金額を決めることとなります。
調停ではお互いが収入に関する資料を提出し、婚姻費用算定表や標準算定方式をベースとして婚姻費用の額について話し合いを行いますが、調停はあくまでも話し合いであるため、双方の合意がなければ成立しません。
審判
調停でも合意ができないときは、家庭裁判所の裁判(審判)で婚姻費用の金額を決定します(家事事件手続法第39条)。
婚姻費用の分担請求調停が不成立になった場合は、審判申立をしていたものとみなされる(家事事件手続法第272条4項)結果、自動的に審判手続に移行します。そのため、調停の申立に加えて審判の申立をする必要はありません。
婚姻費用分担請求は、調停前置(家事事件手続法第257条1項)ではないため、法律上は調停を申立せずに審判の申立をすることも可能です。
しかし、裁判所の職権で調停に付される(家事事件手続法第274条1項)ことが多いため、まずは調停を申立するのが一般的です。
婚姻費用を計算する際によく問題となること
年金収入の取り扱い
年金収入は婚姻費用の計算対象に含まれますが、職業費がかからないという特殊性があるため、基礎収入を計算するにあたってはこの点を考慮する必要があります。
具体的な計算式は割愛しますが、同じ総収入額の給与所得者と年金所得者とを比べると、年金所得者の方が基礎収入額は高額になります。
給与収入と事業収入がある場合
給与収入と事業収入とでは基礎収入割合が異なるため、給与収入額と事業収入額とを単純に合算しただけでは正確な婚姻費用を計算できません。
これに対する対応としては、総収入を計算する際に、事業収入を給与収入に換算して給与収入と合算する、給与収入を事業収入に換算して事業収入と合算するなどの方法があります。
特有財産からの賃料収入
相続によって取得したマンションなどの特有財産は、原則として財産分与の対象とはなりません。
しかし、夫婦で形成した財産を清算する財産分与と、扶養義務に基づき生活費の支払を求める婚姻費用とは制度が異なります。このことから、特有財産からの賃料収入が婚姻費用算定の計算に含まれるかについては、肯定する裁判例(東京高裁昭和42年5月23日決定)と否定する裁判例(東京高裁昭和57年7月26日決定)があります。
1つの目安として、特有財産からの収入が従前の生活費の原資になっていれば、特有財産からの賃料収入が婚姻費用の対象に含まれる可能性が高くなると考えられます。
高額所得者
総収入が2000万円(自営業者は1567万円)を超える高額所得者の場合、婚姻費用算定表も標準算定方式の基礎収入割合表もありません。
高額所得者の場合、税金の割合が高くなるため公租公課を実額で認定したり、貯蓄率を控除する等の方法によって標準算定方式の内容を修正します。
事案の特性に応じて様々な計算方法がありえますので、適切な主張をする必要があります。
住宅ローンの取り扱い
標準算定方式では、総収入から基礎収入を算出する際に住居関係費を特別経費として控除しています。そのため、住宅ローンの対象となる自宅に義務者が居住しているときは、住宅ローンを支払っていることは婚姻費用を減額する要素として考慮されません。
一方、権利者が住宅ローンの対象となる自宅に居住しているときは、義務者は住宅ローンに加えて自分の住居の費用も支払う必要があります。
この場合、義務者は住居費を二重に支払っていることになるため、婚姻費用の額が一定程度減額されることがあります(住宅ローン相当額が必ず差し引かれるわけではありません。)。
婚姻費用を請求できる期間
裁判所は、「婚姻費用をいつの時期から請求できるのか?」という点につき、婚姻費用の請求をしたときから支払を認めるのが一般的です。
従って、例えば別居を開始してから3年が経過したときに突然婚姻費用の請求をしても、過去3年分の婚姻費用は請求できないのが原則です。
裁判例の中には内容証明の送付時から請求を認めたものもありますが、請求をしても相手方が支払わない場合は早急に調停を申立することを強くお薦めします。
婚姻費用の分担請求を弁護士に依頼するメリット
会社員や公務員の場合
婚姻費用は裁判所が算定表を公表してくれているため、夫婦の双方が会社員や公務員の事案では、弁護士に依頼するか否かで結果が大きく変わらないこともよくあります。
しかし、調停の段階では、離婚の条件と婚姻費用の金額とをあわせて協議することもあり、このような場合には弁護士が事件全体を適切に交通整理することで、合理的な損得計算をできるようになります。
自営業者や高額所得者の場合
自営業者の場合、税金対策のために確定申告書の内容が実際の収入と全く違うことがあり、総収入がいくらかという段階から争いが生じることも珍しくありません。
また、年収が2000万円を超える高額所得者の場合は、婚姻費用算定表や標準算定方式をそのまま使用することができないため、標準算定方式の考え方を正しく理解した上で、事案に応じた適切な修正をする必要があります。
夫婦のいずれかが自営業者や高額所得者の場合は、弁護士に依頼をすることで結果が変わる可能性が比較的高いため、依頼をした方がよい場合が多いです。